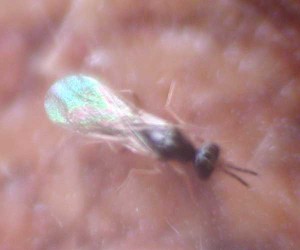Monthly Archives: 2月 2012
Pseudapis mandschurica (Hedicke, 1940) アナアキアシブトハナバチ
オス。県内の畑地帯で複数採集しました。(西日本に分布するものの、本州ではは岡山や京都くらいしか記録がないようですが、今年は山梨でも採集されたそうです。鹿児島では準絶滅危惧種に指定されています。 by 管理人
もう京都や岡山あたりにしか確認されていないのですね。30年前は兵庫の実家の、近所の大豆畑の地面に毎年多数営巣していました。今は完全に住宅地となりました。 by ヒゲおやじ様
アナアキアシブトハナバチは本州では京都府くらいまでしか記録がなかったと思いますが、今年何と山梨県で採れてしまいました!ということで、山梨県で採れたということは中部地方にも生息している可能性があり、関東地方ももしかしたら分布しているのかも知れません。 by ケンセイ様)
2008年9月 鹿児島県/撮影者:Lobo様
Scolia decorata ventralis Smith, 1873 コモンツチバチ
対馬は今,ソバの花の季節です。
ハナアブ探索をしているのですが,ニホンミツバチがたくさん。 ときどきキイロスズメバチが飛んでいました。2008年10月12日 対馬市厳原町小茂田(ソバ訪花)/撮影者:yohbo様
Anterhynchium flavomarginatum tsushimarum (Yasumatsu, 1935) オオフタオビドロバチ対馬亜種
虫好きでハチもたまに撮っているのですが,なかなか名前まで行き着けません。
(オオフタオビドロバチ♀のようですね.対馬の個体群でも,どのくらい黄色い帯が小さくなるかは個体差があるようです.おそらく気になっておられるであろうハグロフタオビドロバチとはメスの頭盾(clypeus)の幅と長さ(オオフタオビ:高さ=幅,ハグロ:高さ<幅)や,オスのaedeagusの先端の形(オオフタオビ:幅広になる,ハグロ:あまり幅広にならない)で見ると確実です.
ハグロフタオビドロバチはむしろエントツドロバチに似ているのですが,エントツでは腹部の第1節背面に横方向の隆起があること,頭盾の先端の凹みが幅広いことで区別できます.参考までに
本州のオオフタオビドロバチはこちら。ハグロフタオビドロバチはこちら。エントツドロバチはこちら。 by みつき様)
2008年10月11日 長崎県対馬市厳原町豆酘崎/撮影者:yohbo様
Protichneumon sp. Protichneumon属の一種
種不明その1。私の住む香川県で、この形に似たハチを寄種に発生した冬虫夏草のハチタケの中間を複数見つけたため、その一つをこの場でお尋ねしたしだいです。(大きい方はヒメバチ科ヒメバチ亜科のProtichneumon属の一種だと思います。 by こにし様) 2008年 撮影者:山鳥様
Picardiella tarsalis (Matsumura, 1912) コクロオナガトガリヒメバチ
この属は産卵管の先端が”くねっ”と曲がっているのが特徴です.こにしさんのおっしゃるように,ヒメベッコウ(ヒメクモバチ)類の巣からもっともよく出てくるヒメバチです.小屋のまわりとかを探索中のメスは見るのですが,産卵の様子は見たことがありません.一度見てみたいものです(この産卵管を使って穴を開けるのかな??).撮影者:みつき様
家屋のコンクリート土台壁面に営巣したヒメベッコウsp.の泥巣群を定点観察しています。
泥巣は壁の縦溝(幅4cm、奥行き2.5cm)の奥に作られてあります。巣作りを一通り終えて主の姿が見えなくなった9月下旬の或る日、別種の蜂が泥巣に居ました。この巣の上をしきりに点検して歩き、コンクリート壁を少し徘徊してまた戻りました。
胸部背中と腹端に一個ずつ白点が目立ちます。触角も途中に白い部分があります。産卵管も見えるので♀でしょうか。蜂の採集・採寸などはしていません。見慣れたヒメベッコウ(体長10mmぐらい?)よりも目視では小柄で華奢でした。(体型と白斑の入り方から判断すると、Picardiella tarsalis コクロオナガトガリヒメバチではないかと思います。普通に採集される種ですし… by こにし様)
2008年9月 撮影者:しぐま様
ハチ目の一種(1) Hymenoptera sp.
種不明その23。2mmぐらいの小さなハチ?がひまわりの茎に留まっていました。2009年9月 撮影者:まあ様
種不明その21。コマユバチの幼虫? 兵庫のじつは甲虫屋です.先日(7月6日)氷ノ山で見たアケビコノハの幼虫です.エライ事になっています. 2009年7月6日 兵庫県氷ノ山/撮影者:虎象様
種不明その20。バラの花の子房に2匹いました。6月25日にも産卵管が短い他はそっくりなハチを見ています。わりと大きく鮮やかな体色でした。2009年6月24日 北海道札幌市/撮影者:zatou様
種不明その19。庭先にいたハチです。2009年5月4日 長野県/撮影者:むいむい様
種不明その18。ハンノキにいた幼虫です。(ハバチの仲間だと思うが種不明。by 管理人) 2009年5月27日/撮影者:混沌様
種不明その17。先日ずいぶんと早いものだと感心しながらオオイヌノフグリの花を撮影したところ、非常に小さな八チが写っていました。オオイヌノフグリの花と比して見当をつけると1~2mmくらいでしょうか。2008年11月26日 埼玉県南の見沼田圃/撮影者:タロ様
種不明その16。ログ材の隙間に枯れ草を突っ込んで有るのを発見!(枯れ草を巣材とするというと、コクロアナバチの可能性があります。竹筒などの既存の穴に営巣することが多いのですが、すき間なども利用するようです。)2006年9月/撮影者:ひと@岡山様
種不明その15。マツについていたハバチのなかまの幼虫です。こんな時期に!とちょっと意外に思えました。2006年12月30日 愛媛県松山市/撮影者:みつき様
種不明その12。ハナバチの一種。河川敷で撮りました。2006年6月 埼玉県/撮影者:バグリッチ様
種不明その11。タマバチ上科の一種と思われる。都内の公園で撮影しました。大きさは4-5mm でした。2006年4月14日 東京都/撮影者:たかの様
種不明その10。タマバチ上科の一種と思われる。2006年4月26日 埼玉県宮代町/撮影者:たえこ様
種不明その9。撮影者:バグリッチ様
種不明その7。コバチの仲間。クスノキ科の特産のムニンシロダモ(本州のシロダモと近縁)の葉に潜っている幼虫を見つけ飼育したところハチらしきものが出てきました。幼虫に寄生していたものと思われる。小笠原父島/撮影者:和田勉之様
種不明その6。コマユバチの一種?の繭。セスジスズメの幼虫の背中に何かの繭が付いていました。2005年9月 東京都日野市/撮影者:Zunda様
種不明その5。コバチの仲間。メタリック・レッドのきれいなハチがフジの葉に付いていた何かの卵(?)に産卵しているように見えました。2005年7月 撮影者:ハンマー様
種不明その4。チョットしなびかけたイヌビワをプラケースに入れておいたら出てきた。2mm位イヌビワの口が開いていた。体長1.7mm。撮影者:TAK.ECHO様
種不明その3。イヌビワコバチは産卵管がもっと短い、イヌビワオナガコバチの産卵管は体長の二倍、こいつはいったい何者?撮影者:TAK.ECHO様
種不明その2。おそらく、クモの卵のうに産卵している所ではないか。撮影者:(;´Д`)ハァハァ様
種不明その1。ツリフネソウで発見した、おそらくハバチと思われる幼虫。棘が特徴なのでオオコシアカハバチかと思いましたが、幼虫の体色が一致しません。2004年9月 撮影者:一寸野虫様
Apis mellifera Linnaeus, 1758 セイヨウミツバチ
多摩川付近遊歩道脇でサルビアの花に来ていました。ハチが飛び去ろうとした瞬間、クモがこれを捕捉しました。 このクモの名は何というのでしょうか? クサグモ、またはコクサグモかと思いましたが、腹部の文様が異なるようで疑問のままです。
クモがハチを捕捉してものの30秒も経たないうちに小さなハエかハチのようなものが最大5匹までハチに群がってきました。クモの獲物をちゃっかりお相伴に与ろうとしているようですが、この昆虫は何というのでしょうか?
ほんの短い間に命の糸が断たれるもの、命を繋ぐもののドラマが展開しました。2016年6月23日(木) 東京日野市/撮影・投稿者:カワセミ様
(写真のハチは、セイヨウミツバチです。クモについては、専門外なのでまったく見当もつきません。捕らえられたハチに群がってきたのはハエの仲間ですが、種名までは私にはわからないですね。by 管理人)
旧掲示板ではたかちゃんでお世話になりました。クプクプという名前でこれからはよろしくお願いします。2008年4月 撮影者:クプクプ様
ヤツデについて少し調べてみたところ、花の形に二種類あることに気付きました。最初は雄花と雌花の違いかと思いましたが、厳密には雄性期と雌性期というのがあるそうです。はじめに雄花が咲き、花粉を出すと、同じ花が雌花にかわるようです。これは近親交配をさけるしくみだそうです。というわけで、私の写真は雌性期のようです。2006年11月 東京都多摩地域/撮影者:高ちゃん様
サザンカ、チャノキの花期がおわりに近づき、今はちょうどヤツデの花に昆虫が集まっていますよね。ウチの近所でもヤツデにニホンミツバチが来ているのを見かけたのですが、人様の庭に生えていたので撮影できませんでした。先日、ウチからちょっと離れたところに撮影できそうなヤツデを見つけ、ニホンミツバチを写そうと、後日、カメラを持っていったところ、びっくり、花に来ているのはセイヨウミツバチのようでした。2006年11月 東京都多摩地域/撮影者:高ちゃん様
ネジバナに訪花。2004年6月 撮影者:tombow様
Apis cerana japonica Radoszkowski, 1887 ニホンミツバチ日本亜種
ニホンミツバチが活動開始しました。黒いのは飛んでいる影です。今日は結構寒かったのにねー。2006年2月26日 撮影者:TAK.ECHO様
日が当たって暑いのに、入り口にタクサン、防衛隊でしょうか? 2006年8月 撮影者:TAK.ECHO様
オス。2006年5月1日 東京都東村山市/撮影者:ぼんぶす様
お寺のお堂に住んでいる。2005年4月 撮影者:TAK.ECHO様
セツブンソウに訪花。2005年3月 撮影者:TAK.ECHO様
ネズミモチに訪花。2004年5月 撮影者:tombow様
Bombus honshuensis (Tkalcu, 1968) ミヤママルハナバチ
蜜を吸っているのはナギナタコウジュです。(区別点は後脚脛節外側の末端側に無毛域がある(ヒメ)か、ない(ミヤマ)かです。この写真では、一面に毛が生えているように見えますので、ミヤママルハナバチでしょうか。)2006年10月10日 栃木県那須塩原市/撮影者:kuwachan様
Bombus ardens ardens Smith, 1879 コマルハナバチ本州亜種
サンゴジュに明らかに大きいコマルハナバチと見るからにワーカーと思われるコマルハナバチが混在していました。今の時期の大きな個体は今年の新女王なのでしょうか?(文献によると、コマルハナバチの新女王は北関東では6月中旬頃から出始めるそうなので、新女王である可能性は十分高いと思われます。by 管理人) 2012年6月/撮影者:KLX様
コマルハナバチとクロマルハナバチの同定ポイント。両種のメスの同定ポイントが不明確なような気がして・・・・ブログなどを見ると、迷いもなく名を書いてあるものも見受けられますが明確な違いがありましたら、ご教授いただけますでしょうか?
(コマルハナバチとクロマルハナバチの区別点は、腹部の毛先で区別できます。クロマルハナバチは、各腹背節の毛の先が切りそろえたようになっていますが、コマルハナバチはそのようにはなっていません。また、コマルハナバチは早春から初夏、クロマルハナバチは春から秋なので、出現時期から判別することも可能です。
ちなみに、コマルハナバチとオオマルハナバチの方が区別が難しいです。腹部第2節に明色の帯があるのがオオマルハナバチ、あっても中央で途切れるのがコマルハナバチと「マルハナバチハンドブック」には掲載されています。しかし、それぞれ個体変異があるので、例外もありそうです。正確な同定には、単眼間の点刻やアゴと複眼の間(いわゆる頬)の長さを見ることが必要です。 by 管理人)
2011年6月 撮影者:KLX様
コマルハナバチのワーカーを撮影しました。コマルハナバチのワーカーの平均的な大きさをよく覚えていないのですが、女王だけで育てたワーカーはもしかしたら小さいのかな、と思いました。女王だけで育てたワーカーと、ワーカーが育てたワーカーで大きさの違いがありますでしょうか。
(女王が育てたワーカーとそれ以降のワーカーの違いについてわからなかったので、手元の文献で調べてみました。「多くの種の野生コロニーでは、第1ブルードの働きバチは、それ以降のブルードのものよりも小型である」(「マルハナバチの経済学」より) ご推察の通り、女王だけで育てたワーカーは小さくなるようです。原因は栄養によるものであろうということです。 by 管理人)
2008年5月1日 埼玉県南部/撮影者:クプクプ様
オス。ブラックベリーの花に来ていました。かなり、動きの速い蜂です。2006年6月 撮影者:tombow様
メス。ブラックベリーの花に飛んできました。2006年6月 撮影者:tombow様
オス。全身黄金色の体毛を持つ蜂に出会いました。葉上に止まっていた体長約17mm位の蜂です。一部の地域では「らいぽん」と呼ばれています。2006年6月6日 東京都小平市/撮影者:ポンちゃん様